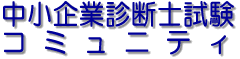
|
ホーム | サイトマップ |
|
|
|
中小企業診断士試験に向けての筆記試験のツボホーム > 中小企業診断士試験に向けての筆記試験のツボここでは、中小企業診断士試験を受験するに際しての二次試験の筆記試験のツボとなることについて、ご説明いたします。 |
中小企業診断士試験に向けての筆記試験のツボ二次試験の筆記試験。 そこで特に重要になるのが「根拠のある内容」と「明確な筋道」です。 まず「根拠のある内容」ですが、書くことに慣れていない受講者によく見られるのが、記載してある内容が「事実」なのか「仮説」なのか「感想」なのかが不明瞭であり混合しているケースです。 事実とは誰が見ても「そのとおり!」というものでなければなりません。 その後に「もし・・・ならば」という仮説と、「私は・・・考えます」という感想を分けて考えることが求められます。これだけでも意識すると文章は変わってくると思います。 次に「明確な道筋」です。 また、文の最後に「結論」として内容をまとめる文を入れたほうが良い印象を与えます。 |
|中小企業診断士試験コミュニティ ホームへ戻る|
Copyright (C) 中小企業診断士試験コミュニティ All Rights Reserved.